
目の疲れをとる方法
『WEBデザイン』の学校に通って習得した知識と技術を活かし、福祉関連の現場で頑張る職員の方々を応援する為のWEBサイト『福祉のお手伝い』を作成し運営しております。
無料画像やお役立ち情報の提供をしておりますので、下記のURLからぜひご覧ください。
無料画像提供サイト『福祉のお手伝い』 n-a-creation.hateblo.jp
今回はそのサイトの『健康情報』より、特別な準備がなくても簡単に実施できる『目の疲れをとる方法』をご紹介します。
普段から目を酷使していて、気づかぬうちに身体が凝り固まって様々な不調を感じているという方は多いのではないでしょうか。
そんなお疲れの方々のケアに活用していただければと思います。
また、以前ご紹介した記事は下のリンクからご覧いただけます。
ページ下方のボタンからは他のページにもジャンプできますので、どうぞ併せてご覧くださいませ (*^-^*)

健康情報8
目の疲れをとる方法
日々の自分時間の楽しみ方は人それぞれです。
テレビや動画の映像を観たり、本や新聞を読んだり、手先を使う趣味に没頭したり、その他にもいろんな楽しみ方があると思います。
そういった楽しいひとときを過ごす際、私たちは知らず知らずのうちに自分の目を酷使していたりもします。
目を酷使することによって視力に影響が出ると今まで当たり前に見えていたものが見えなくなり、見えないことによる不自由さはできることの範囲を狭め、やがて大きなストレスとなります。
また、目が疲れると肩こりや頭痛、倦怠感が生じるなど身体的な苦痛も伴います。
皆さんは普段から目の疲れをケアできていますか?
今回は、簡単にできる『目の疲れをとる方法』をご紹介します。



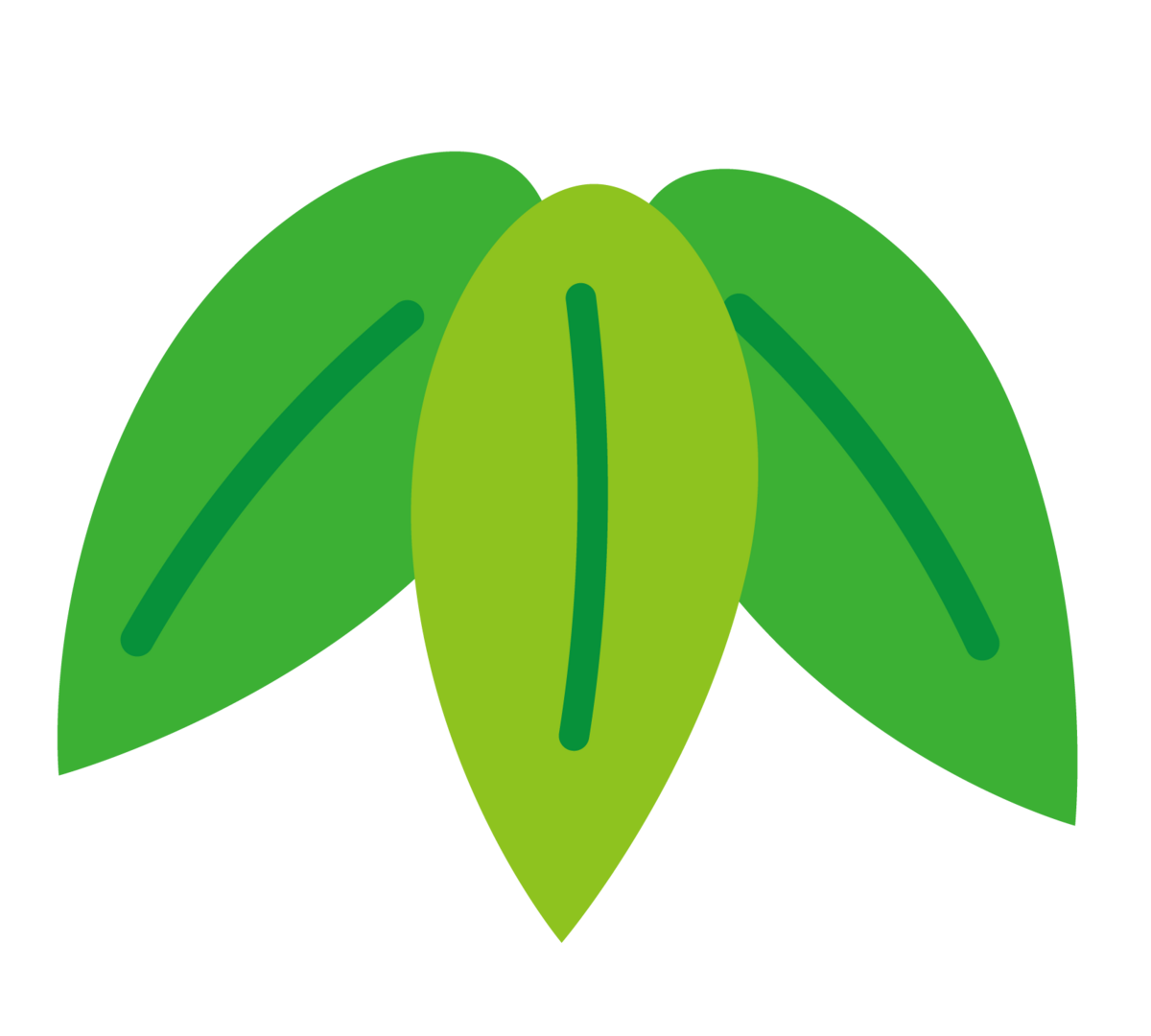
① 目の周りの筋肉を動かす
1.自分が心地よいと思うペースで5~10回程度、連続してまばたきをする。
※ 力を入れる必要はなく、普通のまばたきでOKです。
2.自分が心地よいと思うペースで、顔を正面に向けたまま目線だけを上下に動かす。
※ なるべく自分の真上と真下を見るようなイメージで、上下のセットを5~10回程度。
3.自分が心地よいと思うペースで、顔を正面に向けたまま目線だけを左右に動かす。
※ なるべく自分の真横を見るようなイメージで、左右のセットを5~10回程度。
4.自分が心地よいと思うペースで、顔を正面に向けたまま目線だけを上、右、下、左の順番で動かす。(右回りで1周させる)
※ 目安は3~5周程度ですが、目が回るようであれば無理に実施しないでください。
5.自分が心地よいと思うペースで、顔を正面に向けたまま目線だけを上、左、下、右の順番で動かす。(左回りで1周させる)
※ 目安は3~5周程度ですが、目が回るようであれば無理に実施しないでください。
★ 4と5の動きは、4の右回りの1周と5の左回りの1周を交互に繰り返してもOKです。
★ 一日に何回しないといけないということはないので、目を集中的に使った後や作業の合間に自分のタイミングで実施してください。
★ 転倒防止のため、必ず座っている状態か横になっている状態で実施してください。
★ くれぐれも気分が悪くならない程度に、無理のないように実施してください。



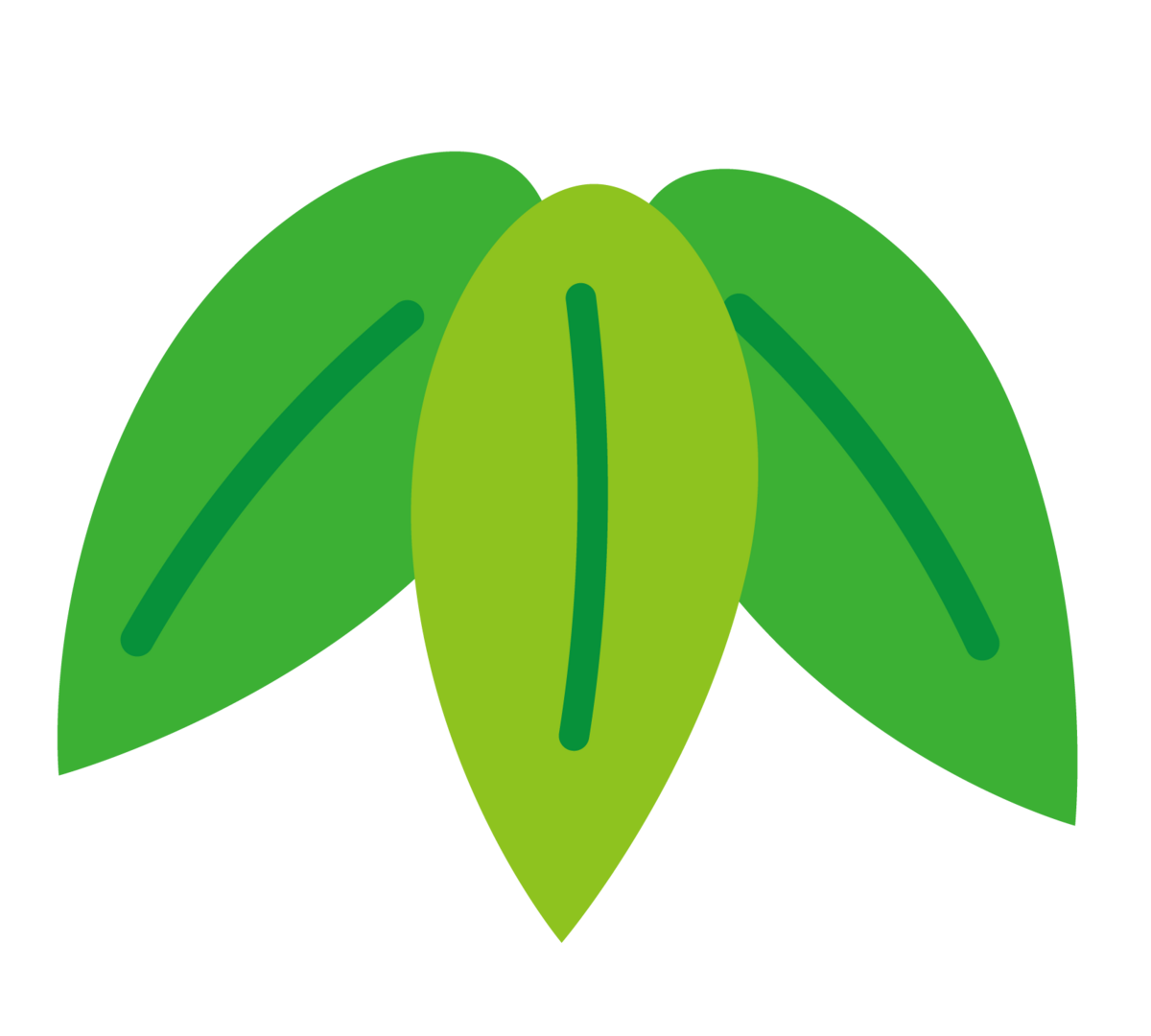
② 遠くを眺める
1.窓から外の景色が見られる環境であれば、なるべく遠くを眺めて目をリラックスさせます。外が見られない環境の場合は、可能な範囲でなるべく遠くを眺めます。
※ 視線の向きはどの方向でも構わないので、空や吹き抜けの天井を見上げても、眼下に広がる景色を見てもOKです。
★ 緑色は目の疲れを回復させてくれる効果があるので、遠くの山や草木を眺めるとより効果的です。
★ 自然の中に見える緑の景色が理想的ではありますが、遠くに見える緑色の建物や看板などでも効果はあります。
★ 緑色が目に与える回復効果は遠くに限らず近くで見ても得られるので、目を休めるために見る緑色のアイテム(絵や物など)を身の回りに置いておくのも良いかもしれませんね。
★ 緑色にもいろんな色があるので、身近で様々な緑色を意識して探してみるのもおもしろそうです。何気ないことが新たな楽しみや刺激となって、目だけではなく脳や心の活性化につながれば何よりです。



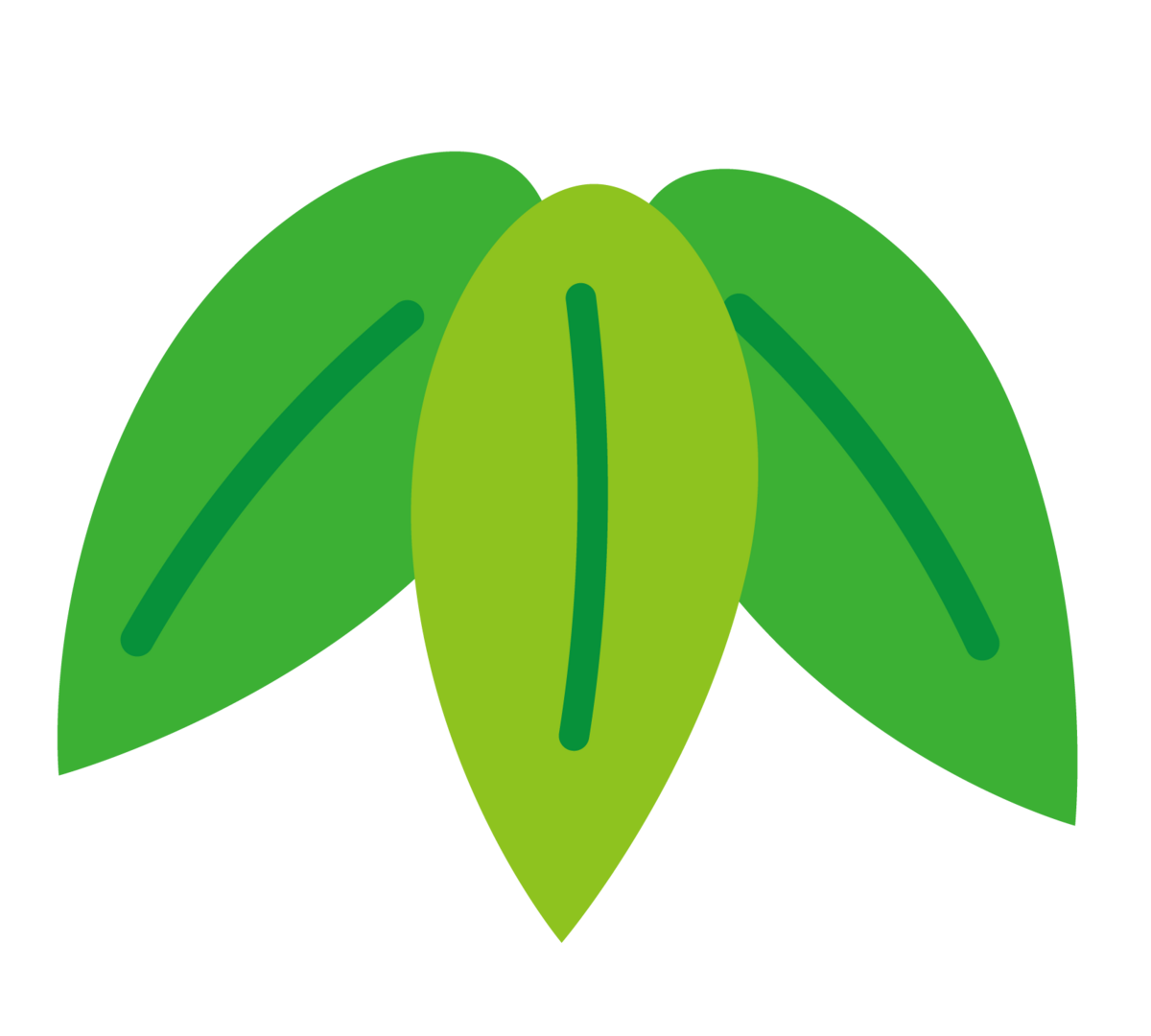
今回ご紹介した2つの方法は、特別な準備をしなくてもお手軽に始められる簡単な方法です。
よろしければ、どうぞ無理のない範囲でお試しください (*^_^*)